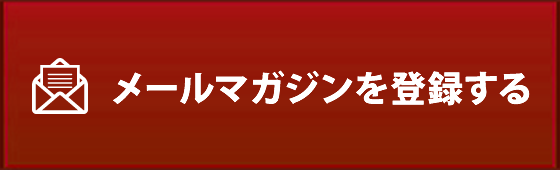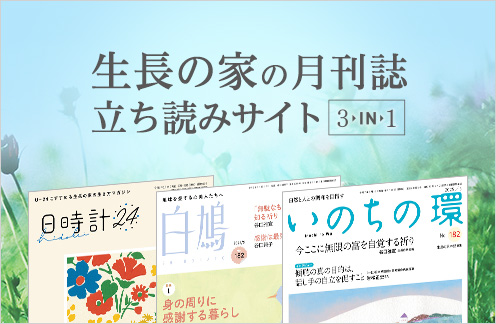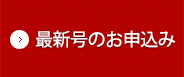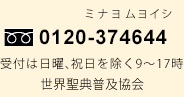平良 剛(たいら・つよし)さん│68歳│沖縄県うるま市
取材/原口真吾(本誌)
子どもの頃に父親から生長の家の教えを伝えられ、それが人生観の基盤となった。社会人となって働き始めてからは職場の人間関係に悩むこともあったが、相手を神の子として受け入れ、そのままの心で向き合うことで乗り越えることができた。さらに、家庭菜園やサイクリングを通して自然と触れ合い、自然に対しても心を開くことの大切を実感するようになった。

「『人間・神の子』の教えが子どもの頃にしっかり入っていたので、大きく道をそれることなくここまで来れたんだと思います」と話す平良さん。沖縄県うるま市の港で(写真/髙木あゆみ)
「おまえは宗教に向いている」
平良剛さんは、父親から生長の家の教えを伝えられた。
「満蒙開拓(まんもうかいたく)移民として満州に渡った父は、戦渦に巻き込まれ、シベリアに抑留(よくりゅう)されました。収容所で日本は侵略者であるという反日思想を押し付けられましたが、帰国後、生長の家を信仰する祖母の影響で教えを学ぶようになって、日本国の理想は、あくまでも平和裡(へいわり)に諸民族の共存を進めることだったと分かり、喜びが湧いたそうです」
ところが、生長の家では神は善一元(ぜんいちげん)であると説いているものの、神の御心に沿うことをせず、日本は戦争に向かってしまったと思った父親は、これからの世のためには、「汝ら天地一切のものと和解せよ」と説く生長の家の教えをもっと広く伝える必要があると、熱心に信仰するようになった。

平良さんもそんな父親に連れられて、小学校4年生の頃から、青少年練成会*1に毎回参加するようになった。練成会を終えて帰宅すると、いつも父親から言葉をかけられた。
*1 合宿して教えを学び、実践するつどい
「あるとき、『おまえは感受性が豊かだから、宗教に向いている』と言ってくれたことが、心に残っています。家では毎朝、父の号令で家族が仏間に集まり、聖経*2を誦げて神想観*3を行(ぎょう)じていました。半ば強制でしたが、父が真理の種まきをしてくれたおかげで、今の私があると感謝しています」
*2 生長の家のお経の総称
*3 生長の家独得の座禅的瞑想法
しかし、中学生になると野球部の活動が忙しくなって教えから遠ざかり、高校を卒業後、福岡県の大学に進学してからも、その状態が続いていた。
思いを素直に伝える
長男だった平良さんは、大学で建築学を学んだ後、地元の沖縄に帰って就職するつもりだったが、県外で経験を積むことも大切だと教師からアドバイスされ、大阪府の港湾工事を担う企業に入社した。
32歳のときに沖縄県の営業所に異動となり、その後、知人の紹介で知り合った女性と結婚した。実家からは離れて暮らしていたが、誌友会*4に来ないかと父親から勧められたため、父親が主催する誌友会の手伝いをしながら再び教えを学ぶようになった。
*4 教えを学ぶつどい

「そんなとき、生長の家の講習会で谷口清超先生*5の講話を聴く機会があり、これからは物質的な豊かさではなく、心の豊かさが求められる時代になるという内容に感動しました。暮らしを便利にする反面、環境に負荷をかける開発工事に自分が携わっていることに思うところもありましたが、やはり心が大切で、心次第で人間中心主義にもなれば、自然と調和する方へ向かうこともできると、気持ちを新たにしました」
*5 前生長の家総裁、平成20年昇天
もう一つ、平良さんの心に響いたのは、「そのままの心で生きる」という言葉だった。職場 では現場監督として、部下に指示を出したり、時には注意をしなければならない立場で、相手を気遣いながら対応しているつもりだったのに、それがかえって裏目に出て、ギクシャクしてしまうことが度々あった。

リビングの窓を開けて風を通す。小鳥が庭を訪れることもあるという(写真/髙木あゆみ)
「そのままの心で生きる」とはどういうことなのかと考えたとき、ある同僚の男性のことが頭をよぎった。
彼はアメリカ人と日本人のハーフで、学生時代は野球部で活躍するなどオープンな性格だった。ある日、食堂で他の社員が手早く食事を済ませている中、彼は「おいしい!」と目を輝かせて味わって食べていた。
「その姿を見たとき、『そのままの心で生きる』というのは、こういうことなんだと感じたんです。それからは部下に対しても、同じ神の子として感謝と親しみの心を持ち、そこから浮かんできた思いを素直に伝えるよう心がけると、コミュニケーションで悩むことがなくなっていることに気づきました」
自然にもっと心を開こう
50歳になった頃、父親が高齢のため、以前のように伝道活動に打ち込むことが難しくなってきた。
「そんな姿を見て、父が魂を込めて灯してきた真理の火を継いでいきたいという気持ちが強くなり、相愛会*6の役を引き受けて、積極的に伝道活動に携わるようになりました」
*6 生長の家の男性の組織
相愛会の主なメンバーは、2024年から無農薬・無化学肥料の野菜作りを始め、採れたての野菜を沖縄県教化部*7のオープン食堂*8で提供している。
*7 生長の家の布教・伝道の拠点
*8 生長の家の各教区が開催する、地域に開かれた食堂

残暑が厳しい9月のある日、たまたま一人で畑作業をしていた平良さんは、ふとこんなことを思った。
「戦死した祖父も畑に精を出していたと、父から聞いたことを思い出しました。祖父も、そして祖父の両親も、皆家族のために畑を耕して、いのちを繋いできたんだと、先祖に対して感謝の気持ちが湧いてきました。土に触れることで、人間としての自然なあり方に戻れるように感じます」

「人と接し、自然に触れる中で、自分がいま、何を感じているか、心の声に耳を澄ませることが大切なんですね」(写真/髙木あゆみ)
また、自転車に乗り、緩やかに流れていく雲や山、海、道端の花などの景色を眺めていると、心が震えるような感動を味わい、自然と心が言葉なき会話をしているように感じるという。
「私たちは自然に対して、もっと心を開かなければならないと感じます。心の声に耳を澄ましていると、自然も人間も、神において一体のいのちを生きていることを教えられますし、自然と人、天地のすべてのものに感謝の心を持ち、そのままの心で接する生き方を、これからも心がけていきたいと思います」
南国の太陽に負けないくらいの、カラリとした笑顔で語った。